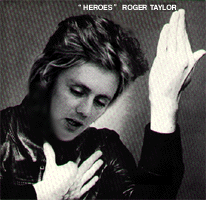|
“クイーンはとっても不器用!?”
評論家は、そしてファンは、クイーンの音楽をいろいろなジャンルの中で語ってきた。
ロック、ハード・ロック、ヘヴィ・メタル、グラム、ポップス、ソウル・・・あらゆるジャンルの中で語ってきた。
他のアーティストには類を見ないその幅広い音楽性は、ある意味クイーンと言う名の一つのジャンルなのかもしれない。
よく「クイーンはクイーン」と言われるが、それはまさに「クイーンのジャンルはクイーン」と言っているようなものである。
ということはクイーンはクイーンというジャンルの中から抜け出せなかった、とても不器用なバンドなのではなかろうか?
好きな音楽も、真似ではなくクイーンとして消化してしまう、
そんな100m先から聴いても分かるクイーンの音楽を、四人に心行くまで語ってもらう。
|
PART ONE
グラムの枠には収まらない!

|
「まただよ、ホラっ」
「グラムのカス?」
「よく言うね、まともに僕らの音楽聴いたこともないのに」
「ホント、ホント」
「“ボランもスレイドもモットも皆一緒”っていうのがおかしいね」
「それに、ロキシーまでグラムだって」
「スイートと僕らの共通点ってなんだい?」
「要するに見た目が派手でケバケバしいって言いたいんだろう」
「大事なのは音楽じゃないのかね」
「彼等の中にだって素晴らしいバンドがいるのに」
「グラムやってる連中に失礼極まりないね」
「でも僕らはグラムの枠の中には納まりきらないぜ」
「そうそう、僕がグラムの道を選ぶならもっとうまくやるよ」
「どんな風に?」
「はっはっは、ボランそのままじゃないか」
「スライダーならぬスレンダー!」
「単なる病気だろ?」
「・・・・・・」
「黙るなよ、暗くなるだろ」
|
|
|
PART TWO
ライヴじゃ俺達も結構ラフだぜ!

|
「アメリカはあまり好きになれないねぇ」
「でも音楽にはいいのもあるぜ」
「プレスリーは好きだよ」
「そうそう、彼のロックン・ロールは最高だね」
「僕はソウル・ミュージックが一番だな」
「ゴスペルもいいよ」
「今日のライブで、スプリングスティーンを演らないかい?」
「ああ懐かしいね、みんなで彼のライブを見に行ったよな」
「でも、僕らのイメージとは随分かけ離れるな」
「クイーンの熱いストリート・ロック?」
「演れないことはないと思うよ」
「でも、君には似合わないね」
「何言ってるんだい、僕にもやれるぜ、ホラっと」
「ちょっと違うんじゃないの?違和感アリアリだぜ」
「そうかい、まあ僕にはもうちょっと上品な服が似合うけど」
「そういう違和感じゃないよ」
「じゃあ、何だい?」
「弾けないくせにギターを持ってることだよ」
「・・・・・・」
|
|
|
PART THREE
常に新境地を開拓するのさ!
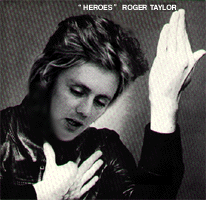
|
「変化することを怖がらない奴はスゴイね」
「僕らのことだろ」
「いきなり結論かい!それじゃ話が進まないだろ」
「それじゃあ、例えば?」
「ボウイだよ」
「なるほど」
「ほらこのベルリンで活動して頃なんかスゴイよ」
「僕はあまり好きじゃないね、前の方が良かった」
「でも常に彼は新しいものにトライしているよ」
「トライっていうより、これは実験音楽そのものだよ」
「僕もいろいろ実験したいことがあるなぁ」
「ソロで演ってくれよ」
「分かったよ」
「でも君のボウイ好きは分かるけど、ちょっとタイプが違うな」
「そうかい、マネもできるぜ、ホラ」
「ダメダメ、照れがある」
「そうそう彼はもっと気取ってるよ、そしてそれがサマになる」
「そう 君は後ろでイスに座って叩いてるのが一番」
「・・・・・・」
|
|
|
PART FOUR
音楽的センスが違うんだよ!

|
「僕らの音楽には土の匂いがしないって」
「都会的だからね。我らシティ・ボーイズ!」
「良く言えばね」
「アラバマの生活を歌えないのは事実だ」
「かと言って、AORでもないね」
「大都会の大人の音楽?四人でスーツ着て?」
「よしてくれよ、そんな甘ったるいの」
「僕は嫌いじゃないな」
「君も結構好きだろう?」
「僕は見た目が都会的っていうのには興味がないよ」
「港で薔薇でも持って立ってよ。よっ、マーティ・バリン!」
「勘弁してくれよ」
「分かった、音楽的センスの問題だね」
「そう、分かってくれたようだね」
「ジョー・ジャクソンみたいな音楽かい?」
「今回はこれ。ドナルド・フェイゲン。僕もこんな風に・・・」
「似合うって言えば似合うけど」
「普通・平凡・サラリーマン」
「・・・・・・」
|
|
ということで、ここで彼等四人は“他人の真似も出来ないことはなかった”と語っている。
しかし、そのどれもがハマってはいない。どうやら他人の真似をするには、四人の個性があまりにも強すぎたようだ。
その点で、「クイーンはクイーン」という言葉の意味が、「ストーンズはストーンズ」という言葉の意味とは微妙に違うことが分かる。
それは「クイーン」という言葉を口にしたとき、そこに描かれるのが、明らかにメンバー個人の姿ではなく、必ずこの四人の姿だからである。
メンバーの誰かがクイーンをクイーンたらしめているのでは、決してないのである。
つまり「クイーンという名のジャンル」とは、「四人の個性のぶつかり合い」に他ならないのだ。
もしぶつからなかったら、クイーンはフレディというジャンルに納まったり、ブライアンというジャンルに納まっていたかもしれない。
しかし、そうはならなかった。メンバー個々よりも、常に大きい存在であり続けたのがクイーンだった。
クイーンが納まることができたジャンルは唯一「クイーン(集合体)」だけであった。
ハードロックで暴れても、ブラックに近づいてダンサンブルになっても、どうしてもクイーンになってしまう。
「クイーンはクイーン以外できない」・・・ 私たちはその不器用さが好きでたまらない。
|